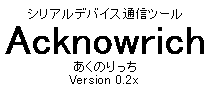 |
シリアルデバイス通信ツールの紹介
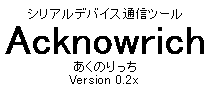 |
![]() Acknowrich
Acknowrich
PICとパソコン間でシリアル通信のテストを行います。まずは、パソコン側の通信ソフトが必要です。PICターゲットボードのハードの確認のため、必ず動作の確認ができている通信ソフトを使ってください。ここでは、ChuChuさんのAcknowrich(あくのりっち)をご紹介しましょう。送受信ともに 16進ダンプもASCII 表示もでき、解析に便利です。
下記のホームページからダウンロードできます。〔注〕2000.12現在 Ver0.2x (Ack020.lzh)
http://www.biwa.ne.jp/~chu0296/
まずは、圧縮ファイルをダウンロードし解凍します。適当なディレクトリにコピー(インストール)します。
詳しくはAcknowrich.hedを参照してください。レジストリは使用していません。
Acknowrichは、シリアルデバイス(RS232C)を扱う通信ソフトウェアです。通信のテスト、解析等を目的としています。そのため、巷にある通信プログラムとは少し違っています。
それでは、Acknowrichの特徴を紹介していきます。(Acknowrich 添付ファイルを参照)
![]() Acknowrichの特徴
Acknowrichの特徴
Acknowrich.exeを起動します(図1)。
 |
| 図1.Acknowrichの画面表示(一部抜粋) |
次にシリアルデバイス(RS232C)を開きます。「ファイル(F)->シリアルデバイスを開く(O)」のデバイス名(ポート名)を指定してオープンします。ここでは、COM1を指定しました。現在開いているポートや、他のアプリケーションで開いている(特にモデム)ポートまた、
実装されていないポートを開こうとすると失敗します。
![]() Acknowrich全体の説明紹介
Acknowrich全体の説明紹介
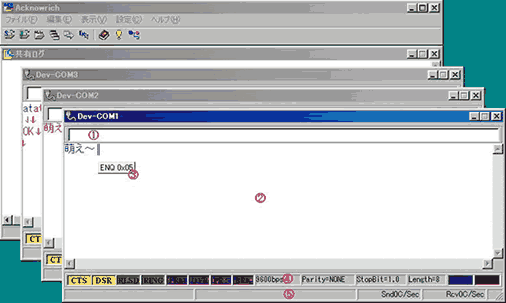 |
| 図2.Acknowrich全体の説明 |
![]() シリアルデバイスの動作設定
シリアルデバイスの動作設定
(1)一般
スレッド優先度: 通信スレッドの優先順位を設定します。この優先順位はOS全体からの優先順位です。特に必要が無い限り"中"にしておいてください。通信の精度を上げたい(文字落ちが発生したりとか)時は高くします。高くすればする程そのスレッドの応答が良くなりますが、そのスレッドの負荷が大きくなるのでUIの応答が悪くなる可能性があります。最低にした時のみ、そのスレッドはシステムのアイドル中のみしか動作せず、他のスレッドが実行中に実行できない
(割り込めない)ため注意が必要です。
常駐プロトコル: エコーバックモードなど常時実行しておく通信プロトコルを指定できます。
(2)通信パラメータ
通信ドライバへ通信パラメータを設定します。
なお、「通信速度、パリティ、ストップビット、データ長」の設定は通信デバイスウィンドウ上で直接(右クリック)で行います。
フロー制御:
ハードウェアフロー制御 CTS, DSR, RTS, DTR
ソフトウェアフロー制御 XON/XOFF
を設定します。
バッファ : 通信ドライバの送受信バッファ、ソフトウェアバッファの設定を行います。ドライバ送信バッファの値を小さくすると、ログ表示での送受信タイミングの精度が向上しますが、
送信の効率は下がります。ドライババッファの設定は通信ドライバによってサポートされていないかもしれません。
また、この値は推奨値となるのでドライバが必ずこの設定で動作するとは限りません。ソフトウェアバッファは送受信データをソフトウェアリングバッファでバッファリングしています。
大きいほどデータ取りこぼしが少なくなります。
(3)データ
ログ関係の設定をします。
ログデータ: 送受信各データを記録するかを設定します。
送信フォント/受信フォント: 送受信の各フォント色、フォント属性を設定します。ログ表示部分及び送受信インジケータに反映されます。
共有ログモード: 送受信のデータを共有ログに記録する場合にチェックします。複数のデバイスをこのモードにすることにより、複数デバイスの送受信データを
混在表示させることが出来ます。このとき送受信フォント色を他のデバイスと違う色にするとをお勧めします。共有ログモードの使い方としてスニファリングがあります。
![]() ログ設定
ログ設定
(1)ログ1
最大桁(TEXT/BINARY): 最大桁を設定します。この桁を超えると折り返します。 テキストモード時と、バイナリモード時がありますが、現在はバイナリモード時のみ変更可能 です。
折り返し: いわゆる改行条件の設定です。
ログ更新: ログの更新時の扱いを指定します。最新表示は常に新しい送受信データが表示され、最下部まで行くとスクロールします。固定表示は新しい送受信データにかかわらずスクロールを行いません。
漢字: 表示するときの漢字コードを指定します。
(2)ログ2
定義文字列: 各1キャラクタに対応する定義文字列を設定します。定義したものはログ内でヘルプヒントとして、 表示されます。デフォルトで作者の知る限りの文字列が定義してあります。0x00〜0xffまで各1キャラクタ毎に定義できます。空白は未定義の文字列になります。
自動ファイル保存: 設定すると、記録されたログを自動的にファイル保存します。保存するファイル名は拡張子を付けないで指定します。
拡張子はシリアル番号として付加されます。シリアル番号は「ファイル名.000〜ファイル名.999」の順番に保存されます。
保存は各デバイスウィンドウをクローズするとき又はログをクリアするときに保存されます。
その他の説明事項・詳細については、Acknowrichの添付ファイルやHelpをご参照ください。
 |